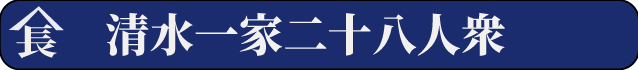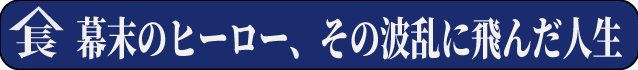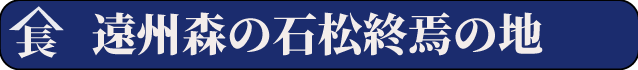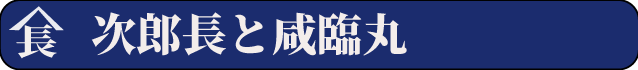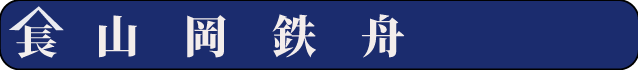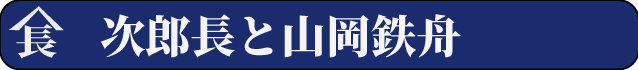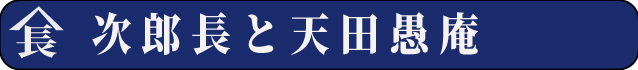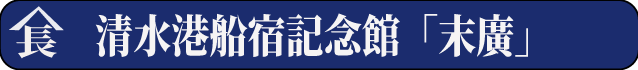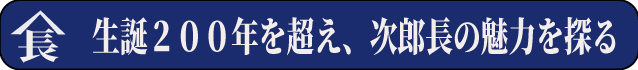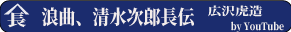次 郎 長 と 静 隆 社
明 治・舞台や映画に登場しない清水次郎長の功績
そのお茶の輸出に、次郎長は後半生を賭けたのです。静岡のお茶を輸出する、
輸出先はアメリカです。輸出の80%ぐらい占めておりました。
その頃、清水港はまだ開港場ではなかったのです。外国に輸出するには開港場
である横浜を経なければならない。
その為に、静岡のお茶は清水港から横浜港へ運ばなければなりませんでした。
お茶は蒸気船で運ばなければならない。
ちょうどその頃に、静岡丸とか清川丸とか、三保丸とかいう蒸気船が造られました。
これらの蒸気船は200トン、300トンの中型でした。ただ、これまでの帆船とは違って、
蒸気の力だったんです。
静隆社(せいりゅうしゃ)という大きな船会社ができます。その船会社を作るために、
次郎長は大変な努力をしました。
静岡には茶町とかあります。ここでは今でも新茶の取れる時期は一晩中作業してますね。
その静岡のお茶を集散する茶商、お茶の商人がおりました。
それに清水港の廻船問屋がありました。清水港四十二軒の廻船問屋(かいせんどんや)
がありまして、それは元和元年(1615年)に家康が作ったものです。
静岡の茶商、横浜の商人達、清水港の廻船問屋の人達、その三者を口説いて、株式会社
ができたのです。
資本金は、三万五千円、今でいえば何百億という静隆社(せいりゅうしゃ)という船会
社ができたのです。
次郎長は影の人物で、株主の名簿にも名前を出しておりません。しかし、次郎長が作った
ようなものなんです。
明治33年、次郎長が亡くなってから数年後に開港場になりました。そして清水港から
直接輸出することもできるようになりました。