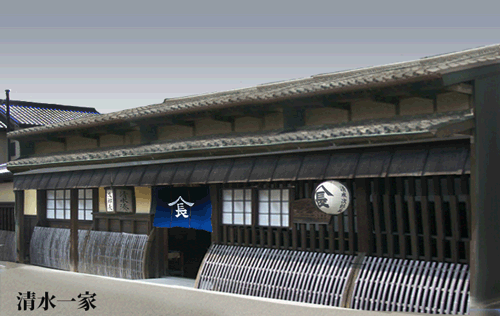残 さ れ た 鉄 舟 の ピ ス ト ル
望 嶽 亭 の 幕 末 秘 話
江戸城総攻撃も間近に近い緊迫した時期である。
こんな時、江戸では主戦派、恭順派に分かれていたが、勝海舟の特命を受けた山岡鉄舟は、将軍慶喜の救命を前提とする江戸城明け
渡しの談判を西郷とするため、駿府に向かった。

すでに官軍の先遣は箱根を越え、宿場の警備は厳重であった。薩摩藩士益満休之助を帯同したのは、官軍陣営を突破する手段だったが、
それでも決死の覚悟なしにはできない任務であった。
途中難なく、三島、沼津、吉原を過ぎ富士川をわたって蒲原、由比に差し掛かったときは、日が暮れていた。
薩唾峠を登ったとき、突然暗闇の中で誰何の声がかかった。一人では突破できないと見て山岡は急ぎ引き返したが、官軍は怪しいと見て
発泡してきた。
薩唾峠の登り口に松永家が代々営む旅館「望 嶽 亭、藤 屋(ぼうsくてい、ふじや)」
がある。ここは蜀山人太田南畝(しょくさんじん おおたなんぼ)も道中記に書留めた東海道の名所である。
身の危険を感じた山岡鉄舟はこの「望嶽亭」に逃げ込み、助けを求めた。

当主の「松永七郎平」は火急の措置を取って奥の座敷に入れ、妻・かくに命じて山岡を漁師の姿に変装させ、着用していたものを捕方
の目に触れないように手早く隠した。
持ち物の中に山岡鉄舟のピストル(フランス製の十連発小銃)があって今も現在松永家に大切に保管されている。

この時、七郎平は清水次郎長に手紙を書き、下僕の栄兵衛に命じて手紙を託け
蔵座敷から秘密の通路を通って海に出て次郎長の宅へ案内した。
この抜口は今も当時のまま保存されている。
次郎長は、七郎平からの手紙を受取り、これから山岡鉄舟を駿府伝馬町「松崎屋源兵衛」宅に案内し、ここに宿泊している東征軍参謀西郷
隆盛と面談して有名な山岡鉄舟の「江戸城無血開城」を成功させる談判となり、これが日本の夜明けを迎える大きな契機となったのである。
実際、教科書や歴史書では「江戸城無血開城」の談判をしたのは勝海舟となっているが、事実は山岡鉄舟が西郷隆盛と談判し、江戸城の
無血開城と明け渡しを成功させたのである。
上記記事の出どころ
「次郎長翁を知る会」会報第2号、次郎長と山岡鉄舟との初の出会い、望嶽亭に残された鉄舟のピストルと江戸城無血開城より抜粋。