次郎長と咸臨丸事件 |
|---|
|
幕末から明治にかけて活躍した偉人・勝海舟は徳川幕府の海軍の発展に尽し、西郷隆盛との交渉を通じ、江戸城無血開城を 成し遂げるなどさまざまな偉業で知られている。そんな彼の異形の一つに、鎖国中の江戸時代に侍を率いて咸臨丸に乗り、 アメリカに渡ります。 咸臨丸は安政4年(1857)にオランダで建造されました。当時の日本には、まだ大型の軍艦を造る技術がありませんでした。 太平洋を横断したという大冒険,この船の最初の船名は「ヤーパン号」と呼ばれていましたが、日本で「咸臨丸」と名付けられ、 「観光丸」についで幕府が持つ2番目の軍艦となり、長崎で練習艦として使用されました。 この船に乗り込んだ著名人としては、木村芥舟、ジョン万次郎、福沢諭吉などが挙げられます。 咸臨丸がアメリカに渡ったのは、渡米使節団の護衛という名目でした。  貴重な軍艦の一隻として期待されていた咸臨丸は、のちに勃発した戊辰戦争に旧幕府艦隊として参戦します。京都の鳥羽伏見で幕を あけた新政府軍と旧幕府軍が戦った戊辰戦争は、徐々に戦場を東へとうつしていきます。旧幕府軍の重要な戦力として新政府軍を迎 え撃とうとした矢先、暴風雨に遭い下田港に入り、修理のため清水湊に停泊しているときに新政府軍に襲われ、白旗を揚げたにも かかわらず砲撃され、挙げ句の果てに乗り込んできた新政府軍に乗組員が全員殺され、海に捨てられてしまいました。   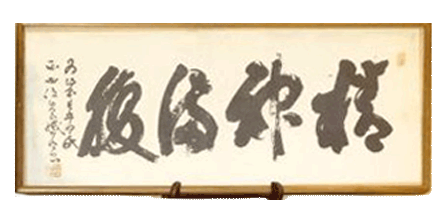
逆賊の船となってしまった咸臨丸の乗り組員たちの遺体は海に漂い、異臭を放っていましたが、新政府軍が「遺体を回収したものは 賊軍と見做し処罰する」というおふれを出したため漁民たちが困り果てているのを見兼ねた次郎長は子分を使って、夜のうちに遺体を 引き上げ手厚く葬りました。 のちに官軍に咎められた時、次郎長は「仏になって仕舞えば、官軍も賊軍もない。地元の人間が手厚く葬ってやるのが人情だ」と 言ったそうです。そして咸臨丸の乗組員たちのお墓は、「壮士の墓」として現在も残っています。 この次郎長の心意気に惹かれた幕臣・山岡鉄舟との交流のきっかけとなりました。 次郎長の侠骨に惚れ込んだ山岡鉄舟は「近年稀に見る侠骨の持ち主だ、小人輩では到底できないこと」と喜び、「精神満腹」と 言う大額を次郎長に送りました。 「精神満腹」とは、次郎長に「悟りとは何か」と聞かれた時に答えた言葉。 |