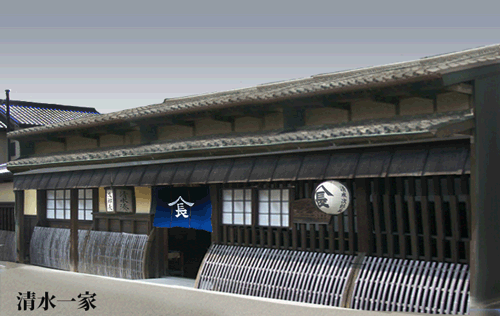遠 州 森 の 石 松 の 実 像
♫ 秋葉路や〜花橘も〜色も映え〜 流れも清き太田川
若鮎踊るころとなり〜 松のみどりも色もさえ
遠州森町良い茶のでどこ 娘やりたやお茶摘みに
ここは名代の火伏せの神 秋葉神社の参道に 産声上げし快男児
昭和の御代まで名を残す 遠州森の石松を 不便ながらも 努めましょう〜♫
とありますが、これは森町茶業青年研究会、島房太郎氏の作った枕司であります。
ところが、ここに大きな誤りが潜んでいました。明治時代に人気を博し「次郎長伯山」と言われた講釈師三代目神田伯山や昭和時代に
一斉を風靡した二代目広沢虎造の名調子の代表作となった次郎長関連の中でも特に人気を博した
「森の石松」ですが、遠州森町の生まれではなかったようだ。実は三州三河の生まれで、「三州三河の石松」
と言うのが本当らしい、遠州森町で生まれたということを証明するものは何一つ残っていないが、石松は森町に
とっては恩人であること言う事である。石松のお陰で森町のお茶は一段と声価を高め、観光森町
は脚光を浴びることとなった。
実は森町がお茶の産地として有名になったのは明治になってから、それは石松は森町で生まれたという
作り話のおかげ、そして「秋葉神社の参道に産声上げし快男児」という一説にも嘘が潜んでいた。
秋葉神社が出来たのは明治になってからで、石松存命の頃にはまだなかったということ。
石 松 の 生 い 立 ち
石松の生家山本家は、当時三河国八名郡半原村堀切(ほりきり)・現、新城市富岡字堀切平で屋敷跡も一反歩(10アール)
もある広さで現在は農地で栗畑となっているが、当時使われていた井戸だけは今も残っている。
山本家の先祖は、信州諏訪藩の藩士であったが何らかの理由により主家を浪人して、三河の堀切で百姓となった。
百性といっても苗字帯刀を許された郷士で、代々山本壮二郎を名乗り、名主、庄屋を努めていた家柄で、洞雲寺境内に
ある山本家先祖の墓地には立派な墓碑も立ち並んでいる。
少 年 時 代 を 遠 州 で
石松の母「かな」は山本家の「助治」のところに嫁ぎ二人の子どもが生まれ長男は夭折したが次男の石松が残った。
石松は、森町で「新屋」という旅館を営んでいる中根安雄氏の七代目新寅」という人の家に預けられ、少年時代を14歳ころまで育て
られた。
その頃の石松は、体格もよく大人顔負けの力持ちである半面、乱暴者でいささか持て余していた。
たまたま清水の次郎長が兄弟分の森の五郎を訪ねた時、新寅のところに立ち寄りじっと石松の動作を見ていたが、「この小僧は見どころ
がある」といって貰い受け、清水へつれて帰った。
石 松、頭 角 を 現 す
清水一家に引き取られ、大政、小政や先輩たちにしごかれて、侠客社会に溶け込み、20歳を過ぎた頃には、清水一家の中でも頭角を現す
までになった。
石松の叔父、稲吉庄右術門応貞は仙台の人が編み出した愛宕流剣術,槍術,捕手術等の免許皆伝の達人で、弓術も日置流の奥義を秘めた
名士であったと言われている。
そのことを石松が「俺の叔父は滅法剣術が強いぞ」と言ったことから庄右術門応貞は他ならぬ甥の石松がお世話になっている清水の
次郎長の頼みとあって、一家の若い衆に剣術の指南をすることになった。
さすが次郎長が見込んだ通り、石松は生まれながらにして剣術の素質に恵まれ、めきめき腕前も上達し、次郎長の子分としてなくては
ならない存在となった。
広沢虎造の浪曲の中では、石松は「片目で、酒が入ると虎狼だが、お人好しで、少しおっちょこちょい、義理人情に熱い人物」として
描かれ、清水一家の名物男となった。
浪曲や映画のなかで石松は片目として扱われているのは、次郎長ものの元になっている「東海遊侠伝」の作者・天田五郎が石松を
片目片腕の「豚松(三保の松五郎)」と混同したものと思われる。
また、実物の石松と出会った正岡子規は「石松は片目でもなければ、吃りでもない」と書き残している。
石松のイメージは、講談師、浪曲師たちがそれぞれ勝手なイメージで作り上げられたものでした。